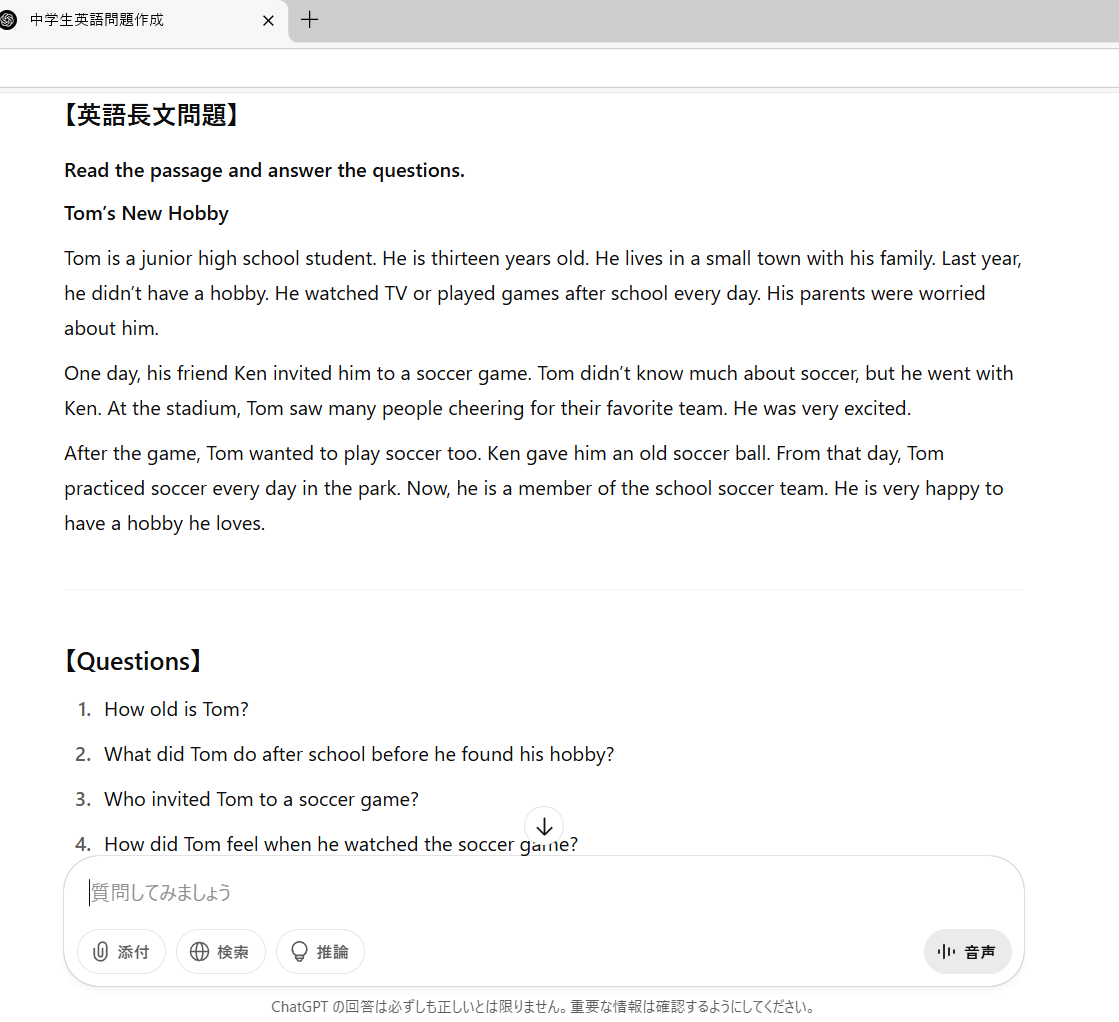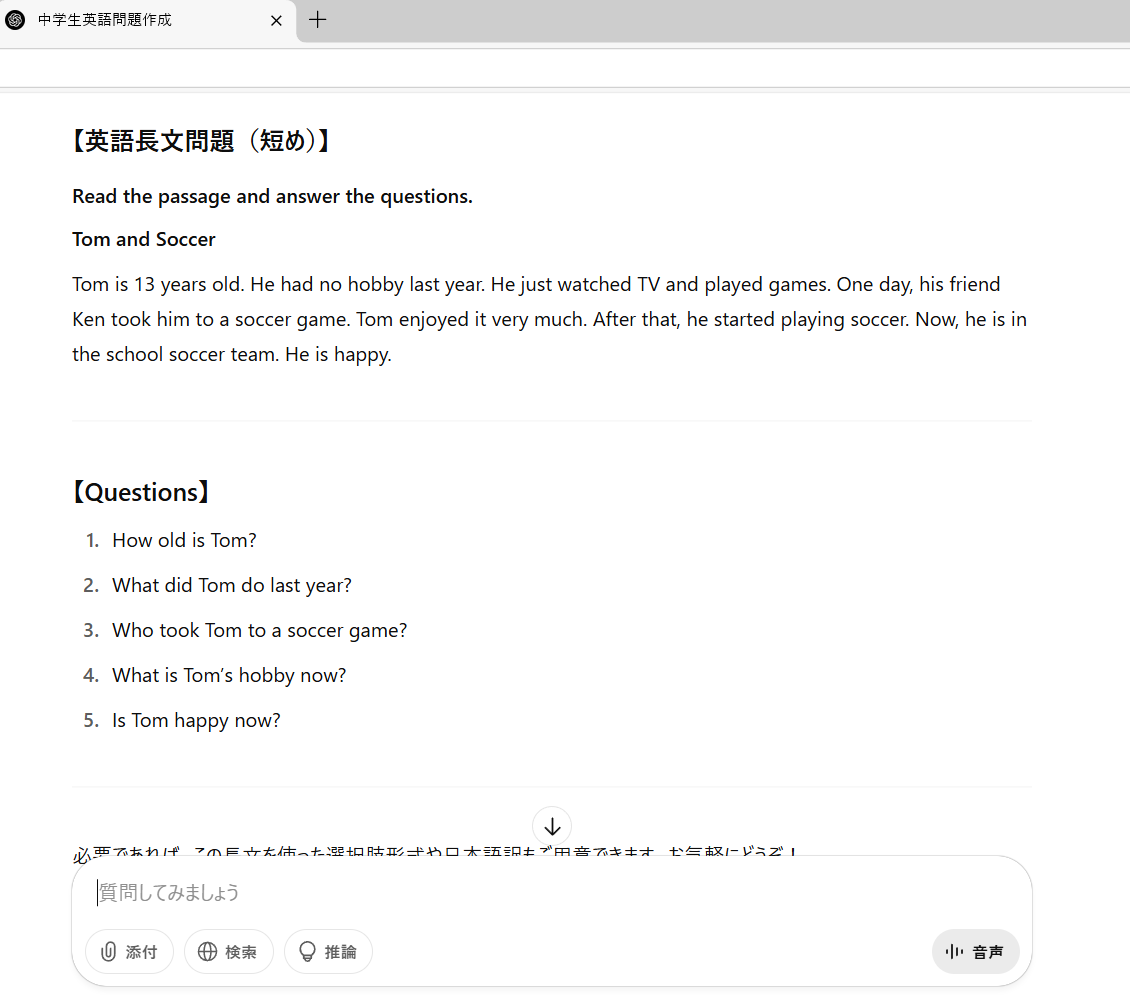今朝、アイスコーヒーを買いに近所のコンビニに行きました。
「ついこの前まで100円やったのに、いつからどこも140円になったんやろ…。高い…。悲しい…。」
コンビニでコーヒーを買うたびに毎回このように心の中で愚痴りながら、今回もお金を支払いました。
2台あるドリップマシーンが両方とも使用されていたので、少し離れた所で待っていました。
そのうち1人のお客さんは、小学生中学年ぐらいの女の子でした。
どうやらお母さんが買ったコーヒーをその女の子がいれているようでした。
「ママー、ストローってどこにあるの?」
「この砂糖のジュース(※ガムシロです)も入れるんやんな?」
ATMを操作しているお母さんにいろいろ聞きながらコーヒーをいれていました。
コンビニのコーヒーはふたをするのに少しコツがいりますよね?
その女の子もそのふたをはめるのに苦戦していました。
「あっ、ちょっと指についちゃった。」
そんなこともつぶやきながら、お母さんのために一生懸命コーヒーをいれていて、その姿にほっこりしていました。
そのとき、その女の子がコーヒーに入れたガムシロのごみがフロアに落ちました。
女の子はふたをするのに一生懸命で、落ちたことに気づいていませんでした。
そうこうしていると、もう1台のドリップマシーンが空いたので、私はそこでコーヒーをいれました。
そしてコーヒーが抽出されている間にそのガムシロのごみを私が拾ってゴミ箱にいれました。
それには何の裏もありません。
その女の子はごみが落ちたことに気づいてないようでしたし、ふたをするのに一生懸命でしたし、私もコーヒーができあがるまでひまだったので、何も深く考えることなくそのごみを拾って捨てただけでした。
するとその女の子が私に気づいて「ありがとう」と言ってきました。
お礼を言ってくれるなんて全く思っていなかったのでびっくりしましたが、「いいよ。どういたしまして。」と私も言いました。
そしてふたも無事にはまり、お母さんのところに歩いて行きました。
私のコーヒーもできあがりふたをしめているときに、その女の子とお母さんがコンビニを出ていくのが目に入って、そちらに目をやりました。
すると、その女の子が入口すぐ横にあるごみ箱の下に落ちていた1枚の紙切れ、おそらくATM使用後に出てくる明細だと思いますが、それを拾ってごみ箱に捨てました。
そして私のほうを見て、にこっと笑ってコンビニを出ていきました。
こんな素敵な朝があるのかと感動しました。
子どもは本当に純粋できれいな心を持っています。
あの子の笑顔は忘れることはないでしょう。
こんな素敵な朝になるのなら、140円なんて安いもんですね!